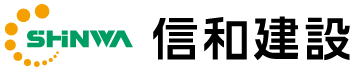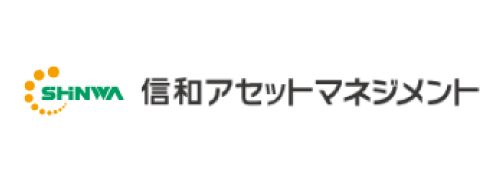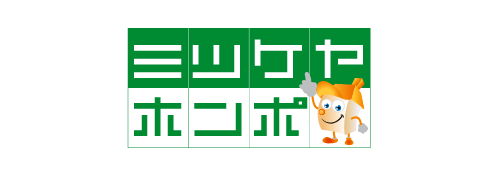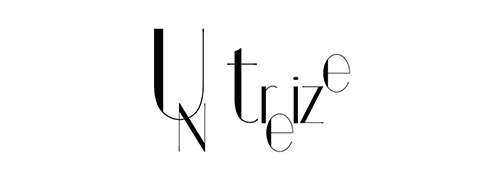貸付用不動産の評価方法の見直しについて
これから相続対策を考える不動産オーナーの方には大きく影響する内容であるため、現時点では詳細が明らかではない部分もありますが、まずは大まかな改正の内容について抑えておきましょう。
1.改正の背景
近年、不動産や株式などの評価額を圧縮するスキームが広く利用されており、課税庁としては財産評価基本通達6項(この通達の定めにより難い場合の評価)に基づく課税処分を行うことなどで個別に対応してきました。
この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。
その後令和4年最高裁判決をきっかけとしてマンション通達が発出され、分譲マンション等の区分所有不動産の評価については、一定の見直しが行われました。
しかし、同通達が適用されない一棟所有の賃貸用マンションをはじめとする貸付用不動産を利用したスキームはその後も散見されており、評価通達6項により個別に対応せざるを得ない状況が続いていましたが、このような対応について、納税者の予見可能性といった観点からの批判があり、評価方法の明確化が要請されていました。
また、市場価格と相続税評価額とのかい離が大きいことも問題視されていました。
不動産市場における貸付用不動産の価額については、主に収益性によって価値判断が行われるため、一般的に貸家の賃貸割合が高くなると市場価格が高くなります。
一方で、財産評価基本通達における貸付用不動産の価額は、借家人の支配権による利用の制約等を考慮して評価するため、賃貸割合が高くなると相続税評価額は低くなる関係にあります。
このような市場価格と相続税評価額とのかい離を利用して、相続税対策を目的とした駆け込みでの物件取得や、物件そのものの希少性等によって貸付用不動産が高値で取引されている事例が確認されています。
相続開始の直前に一棟賃貸マンションの駆け込み取得を行ったケースでは、取得価額21億円に対して相続税評価額は4.2億円であり、かい離率(取得価額÷通達評価額)は5倍となっています。(このケースでは、相続税は約8億円が軽減。)
こういった財産評価を巡る問題を背景とし、相続税法の時価主義の下、貸付用不動産の市場価格と相続税評価額とのかい離の実態を踏まえ、今回貸付用不動産の評価方法が見直されることになりました。
2.改正内容(税制改正大綱より)
被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額(※)によって評価する。
(※)課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって評価することができることとする。
<経過措置>
上記の改正は、令和9年1月1日以後に相続等により取得をする財産の評価に適用する。ただし、当該改正を通達に定める日までに、被相続人等がその所有する土地(同日の5年前から所有しているものに限る。)に新築をした家屋(同日において建築中のものを含む。)には適用しない。
3.改正内容から考えられることや疑問点など
(1)新たな評価方法は、相続・贈与の5年以内に取得したものが対象となるため、既に5年超所有している貸付用不動産(土地・家屋)については適用されず、現行どおりの評価方法となります。
なお、一定の経過措置は盛り込まれていますが、新たな通達が定められた日以降は、自身が5年前から所有している土地上に新たに建築した家屋(賃貸物件)についても、評価見直しの対象になるものと考えられます。
(2)税制改正大綱に記載された「一定の貸付用不動産」の範囲については、現時点では明らかではありませんが、一棟所有の賃貸マンションはもちろん、マンション通達の対象となっている分譲マンション等の区分所有不動産についても、貸付用であれば評価見直しの対象になると考えられます。
なお、貸付用不動産であることの判定をいつ、どのように行うことになるのかは気になるところです。
(3)取得価額を基に評価額を算定する場合、建物については減価償却(定額法)による減価を反映するものと考えられますが、土地について地価変動の影響等をどのように加味するのかは明らかではありません。なお、最後に100分の80を乗じるのは、評価の安全性を考慮したものです。
(4)財産評価基本通達では、賃貸マンションの敷地は貸家建付地として、家屋は貸家として評価しますが、評価見直しの対象となる貸付用不動産について、貸家建付地や貸家の評価減を織り込めるのかどうかは明らかではありません。
(5)小規模宅地等の特例の適用も気になるところです。現在、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等については、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)の適用を受けることができません。(3年縛り)
(※)相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等であっても、被相続人等が相続開始の日まで3年を超えて引き続き事業的規模(いわゆる5棟10室基準)で不動産賃貸を行っていた場合は、上記3年縛りの適用はありません。
評価見直しの対象となる貸付用不動産は5年縛りとなるため、小規模宅地等の特例の3年縛りに変更が無ければ、不動産賃貸業が事業的規模ではない不動産オーナーの場合、次の場合分けになると考えられます。
| 賃貸物件の取得時期 | 取り扱い | |
|---|---|---|
| 小規模宅地等の特例 | 貸付用不動産の評価 | |
| 3年以内 | 適用なし | 適用あり |
| 3年超5年以内 | 適用あり | 適用あり |
| 5年超 | 適用あり | 適用なし |
以前は、個人が取得した土地・建物についても同様に3年縛りの適用がありましたが(旧租税特別措置法69条の4)、財産権の侵害として違憲判決を受けたことに伴い、平成8年度税制改正で廃止された経緯があります。
今回の貸付用不動産の評価方法の見直しに伴い、個人については5年縛りの規制が入ることになりますが、法人の3年縛りについて平仄を合わせる形で見直しが行われるのかどうか、気になるところです。
4.不動産小口化商品について
貸付用不動産の評価方法の見直しと合わせて、小口化された貸付用不動産(不動産特定共同事業契約又は信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一定のものに基づく権利の目的となっている貸付用不動産)についても評価方法が見直されます。具体的には、その取得の時期にかかわらず、課税時期における通常の取引価額に相当する金額(※)によって評価することになります。
なお、通常の貸付用不動産で盛り込まれた経過措置については、不動産小口化商品は対象外となります。
経過措置がない点と、5年以内取得という期間の制約がない点が、通常の貸付用不動産と大きく異なるところです。
(※)課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、出資者等の求めに応じて事業者等が示した適正な処分価格・買取価格等、事業者等が把握している適正な売買実例価額又は定期報告書等に記載された不動産の価格等を参酌して求めた金額によって評価することができます。
ただし、これらに該当するものがないと認められる場合には、貸付用不動産の評価に準じて評価(取得時期や評価の安全性(100分の80)を考慮)します。
5.おわりに
課税庁が問題視しているのは、市場価格と相続税評価額とのかい離が大きい点もさることながら、相続の直前に駆け込みで不動産を取得して相続税負担を大幅に軽減する行為であると考えられます。
日頃から財産の棚卸と相続税のシミュレーションを行ったうえで、計画的に相続対策を進めていれば、今回の見直しの影響を回避することは十分可能だと思われます。
相続対策には時間がかかるという認識をもって、早めの第一歩を踏み出すことをお勧めします。
【情報提供元:税理士法人 FP総合研究所】
https://www.fp-soken.or.jp/